子どもの試し行動とは?
子どもに見られる試し行動とは、
「自分への興味や愛情を確認したい」
「自分のことを受け止めてくれるか」
「どこまでなら受け入れてくれるのか」
を試すために
自覚的に大人を困らせるような行動を取って反応を伺う行動のことを言います。
【試し行動の例】
- 飲食物をわざとこぼす・吐きだす
- おもちゃや絵本をわざと乱暴に扱い、壊す(投げる・破く・折るなど)
- ダメと言われたことを嬉しそうに何度も繰り返す
- 大人の様子を伺いながら走り回る
- 大人や友だちをわざと引っかく・噛みつく

試し行動か判断がつかないときは、以下の2点に注目してみてください。
①気を引くためにわざとやっているか
②大人の顔色を見ながら自分の行動をコントロールしているか
試し行動の原因は?
試し行動の原因は様々で、
ネットで検索すると「虐待を受けた子どもが…」「大人への信頼を失った結果…」など
不安になることも出できますが、一概にそうとは限りません。
お子さんは、ママやパパが大好き。
「ねえ、どれくらい私のこと愛してるのか教えて!」
そんな気持ちが行動に現れるのです。
試し行動は、身近な大人との信頼関係を結んでいく大切な段階とも言えます。

ママは「もしかしたら愛情不足かも??」と自分のことを責めないでくださいね。
これは試し行動かな?と感じたら、正しい対処法で子どもへの愛情を伝えていけば大丈夫です。
試し行動をする子どもの気持ち
次は「試し行動」が起こる背景を見てみましょう。
どれか1つが大きな要因となっている場合もありますが、
年齢や環境、その時々の状況によって違う場合ことが多いです。
ここでは試し行動の背景にある子供の心理を6つ紹介します。
1.甘えたい・愛情を確かめたい
親が仕事で忙しい、弟や妹が生まれたなど、
少し寂しい思いをした後に、このような心理になることが多いようです。
「この人はどれくらい自分を大事に思ってくれているんだろう」
「こんな悪いことをしても、嫌いにならないかな?ちょっと試してみよう」
と、身近な大人の愛情を確認するために試し行動をとってしまうのです。
また、甘えたい気持ちをどのように表出したらいいかがわからず
結果として親を困らせるような行動になってしまうパターンもあります。
ちょっと怒りすぎたな…最近忙しくてじっくり遊ぶ余裕がなかったかも…など
些細なきっかけで子どもが試し行動をすることも。
2.目の前の大人が信頼できる人か確認している
子どもの「試し行動」は親だけでなく、先生やたまに会う祖父母など
身近にいる大人に向けて出てくることもあります。
「この人はどんな人?」
「本当に自分のことを大切にに思ってくれるのかな?」
そんな心理から、子どもなりに大人を試しています。
3.自分を見てほしいが、方法がわからない
ネガティブな行動によって、大人の気を引こうとしているケースもあります。
泣けば、癇癪を起せば、ワガママを言えば
自分が優先される・ママやパパが自分のところへ飛んできて構ってくれる…
子どもにとってはこの方法が一番容易でやりやすいからです。
この場合、子どもに向き合うことと同時に
【ポジティブな方法】で自分に注目してもらう方法を伝えていくことが効果的です。
4.環境の変化による不安
進級・入園・引っ越し、きょうだいの誕生など、子どもにとって環境の変化は一大イベント。
なかなか心がついていかないと、そのストレスや不安が試し行動というかたちで表出してしまうことも。
5.心の傷
これは特殊なケースですが、親の離婚や再婚・虐待・愛着障害などで
心が傷ついていたり不安定な時にも表れることがあります。
デリケートな問題なので、このケースは専門機関や教育機関と連携してより慎重に対処する必要があります。
ではどのように、対処すればよいのでしょうか?
試し行動への対処法とNG対応
子どもの試し行動は、大人にとって困るもの。
そのため、時には感情的叱ってしまったり、無視をしてみたり、「もう知らないよ」と突き放すような言葉で伝えたくなることもあると思います。ただ、逆効果になってしまうこともあるのです。
ここからは子どもが試し行動をした際の対応方法とNG対処法を紹介します。
1.理由を聞く・受け止める
「どうしたの?」「どんな気持ちでやっちゃった?」
など、子どもの感情に寄り添うことが大切です。
また、「うんうん」と目を見て頷いて共感を示してみてください。
これによって、自分の気持ちを受け止めてくれていると感じ、安心感をもって向き合うことができます。
(子どもの話を聞く前に責める姿勢からスタートすると、試し行動がより強く出てしまうこともあります。)
「ちょっと寂しかったんだね」「もっと一緒に遊べるといいよね」と気持ちを表す言葉や、
これからどうするか子どもと一緒に考えられるといいですね。
2.愛情を伝える
子どもが試し行動によって大人の愛情を確かめようとしている場合、
感情的に叱ると「欲しかった愛情」を受け取ることができず、不安が増してしまいます。
子どもの自己肯定感・自己受容感の低下にも繋がりかねません。
①○○な気持だったんだね。 (気持ちの理解と受容)
②ママはどんな○○ちゃんも大好きだよ。 (愛情を伝える)
③でもその行動はよくなかったね。次からこうしてみようか。 (行動の訂正)
この順番での声掛けがおすすめです。
3.よくないことははっきり線引きして伝える
人格否定ではなく、「行動」にフォーカスして伝えることを心がけましょう。
その行動がなぜ良くないのか?どうすべきだったのか?
子どもの年齢や成長に合わせて短くわかりやすく伝えることが重要です。
幼さゆえに、問題行動(ネガティブ行動)しか思い浮かばずについやってしまうのです。
本来とるべき行動(ポジティブ行動)も一緒に伝えてください。
「こうしてくれたらママ○○ちゃんの気持ちがわかるよ」
「次からはこうしたらどう?」
と叱るだけで終わらせず、適切な行動も伝えましょう。
そしてもし子どもがその行動をとることができた時には、大いに褒めてあげてください。
ポジティブなフィードバックを繰り返すことで、子どもの成長をサポートすることができます。
4.スキンシップを増やす
スキンシップに関して注目されているのが「オキシトシン」という脳内物質です。
「オキシトシン」は愛情ホルモンとも呼ばれ、
スキンシップによって子どもと親双方の脳内に分泌されることで
・ストレスを和らげる・ストレス耐性を強める
・緊張を緩和する
・精神的な安定感を得る
などの効果があります。
抱っこしたり、抱きしめたりするだけでなく、
手をつなぐ、頭や背中に手を当てる、膝に手を乗せる、背中同士くっつけるなど、少しの触れ合いでも大丈夫です。その時に合ったスキンシップでよいのです。
(余談ですが、実は男性脳・女性脳でもオキシトシンの出方に差があり、女性脳の場合は優しく触れたり抱っこで分泌され、男性脳の場合は多少激しめの体を動かす遊びなど、刺激が多めのほうが分泌されやすいともいわれています)
また、スキンシップは親と子の信頼関係構築にも繋がります。
感情的なつながりが強化されると、子どもは自分の感情や悩みを素直に表現しやすくなります。
5.過剰に反応しない
試し行動に過剰に反応してしまうと、
「この行動で注目してもらえた。うまくいったぞ。」
という誤った成功体験を子どもにさせてしまうことになります。
そのため、正しい行動だと誤解したまま同じ行動を何度も繰り返してしまうのです。
試し行動が起こった際には、冷静で適切な対応をすることが重要です。
NGな対応
最後に、これは避けてほしいという親のNG対応についてです。
- 無視する:無視をすることで、より子どもを不安な気持ちにさせてしまいます。
- 一貫性がない:この間はよかったに今日はダメ、など親の曖昧な境界が混乱を招くことがあります。
- 思いを否定する:否定が続くと子どもは次第に自分の思いを言えなくなります。受容からスタートです。
- 押し付ける:本当は自分にも考えていることがあるのに…と不満を持ちづづけることに。子どもにも当然思いがあり、選択する権利があります。一緒に考える姿勢が重要です。
- 感情的に叱る:子どもが自分の思いを心の中に留めたまま不完全燃焼で終わるため、試し行動が何度も繰り返されてしまう可能性があります。また、子どもの自己肯定感・自信を奪うことにも繋がります。
上記の対応は、試し行動の悪化に繋がる可能性があります。
逆に、適切な対応ができれば、試し行動が「親子の絆が深まる」きっかけにもなり得るのです。
さいごに
繰り返される試し行動に、
「この子は私のこと嫌いなの?困らせることばかりして!」
そんな風に思うこともあるかもしれません。
試し行動をされる立場からすれば、どうしてそんなことをするのか、不安になりますよね。
しかし、試し行動は「他でもないあなたに、私を受けとめてもらいたい」というメッセージでもあります。
そのため、甘えたい相手や関係の深い相手に出てくることが多いのです。
決して否定的な面だけではありません。
子どもとの関係を強化できる良い機会と捉えて冷静に対応していけるとよいですね。
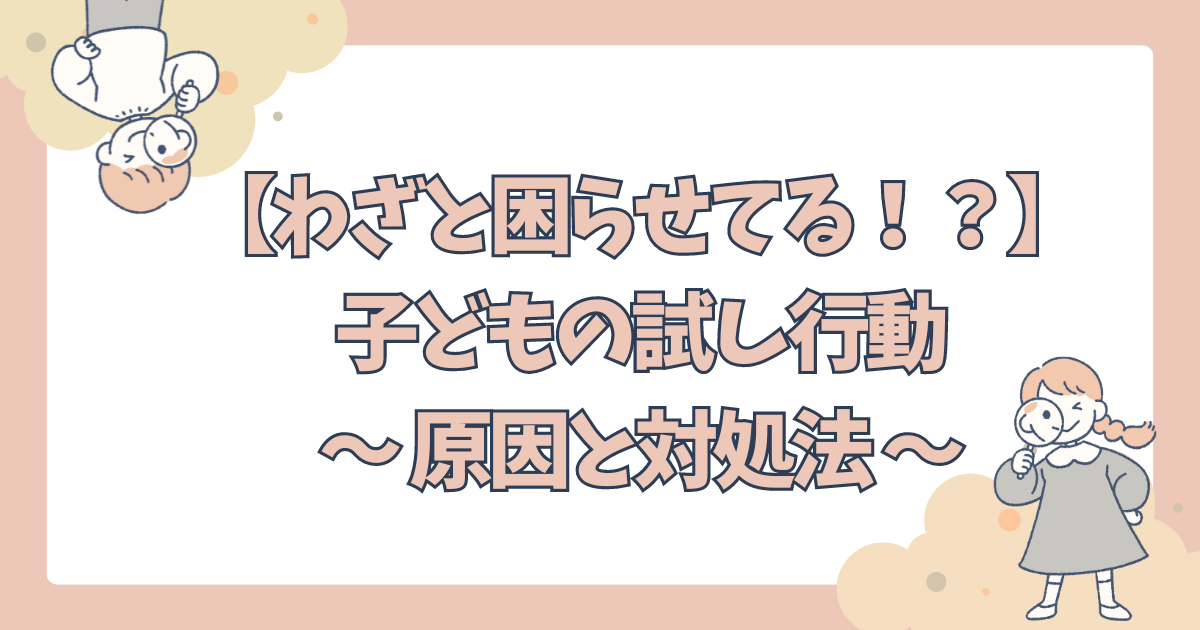
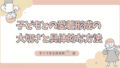

コメント